小学校の音楽授業で使うリコーダーは、演奏後の手入れがとても大切です。
この記事では、ダイソーで購入できるリコーダーの掃除棒の情報から、掃除棒の使い方、リコーダーのお手入れ方法、掃除棒が無い場合の代用品、掃除を怠ったときのリスクまで徹底的に解説します。
一般のご家庭や小中学生の保護者、楽器初心者の方にもわかりやすい内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。

結論から言えば、ダイソー単体で「リコーダー掃除棒」だけを販売しているわけではありません。しかし、ダイソーなど100円ショップでは、リコーダー(縦笛)本体に掃除棒が付属したおもちゃが販売されているため、リコーダー掃除棒を手に入れるには、リコーダー本体ごと購入する形になります。
実際、2019年頃にはダイソーで税込110円(100円+税)のソプラノリコーダーが販売されており、組み立て可能で掃除棒(洗浄用の棒)と収納袋付きでした。
形状もしっかりしていて分解も可能でしたが、音程が学校で使うものとは異なり、実用品というより玩具扱いです。ただし、このダイソーのリコーダーは店舗によって品揃えが異なる可能性があり、常に全店舗で扱っているとは限りません。ダイソーでは見つけられず、セリアで購入できたということもあるようです。
そのため、確実に手に入れたい場合は大型店や新学期シーズンに確認すると良いでしょう。
またセリアやキャンドゥなど他の100均でも、掃除棒付きのリコーダー玩具を110円程度で販売しています。もしダイソーで見つからない場合は、他の100円ショップも覗いてみると良いでしょう。
ダイソー公式情報では専用掃除棒の単品販売は確認できませんでしたが、必要なら楽器店で掃除棒単品を購入することもできます。

ヤマハ YAMAHA クリーニングロッド S PLASTIC CRSをAmazonで見る

前述のように、ダイソーなどの100均ではではリコーダー本体(ソプラノリコーダー)+掃除棒のセットが税込110円で販売されていることがあります。ここでは、その内容や品質、他社製との違いについて触れておきます。
・仕様
ダイソーや他の100均で売られているリコーダーは、多くがソプラノリコーダー(ジャーマン式指遣い)です。小学校で一般的に使われるのもソプラノリコーダー(ジャーマン式)なので外観は似ています。材質はABS樹脂製で、学校教材のプラスチック製リコーダーと同じ材質です。
・付属品
掃除棒はプラスチック製の棒で、長さや形状は一般的なリコーダー付属のものとほぼ同じです。ガーゼ(掃除用の布)は付属しないケースが多いので、自分で用意する必要があります。100均リコーダーにはグリスは付属しないことが多いです。掃除棒自体の形状は一般的なものと変わりありません。
・価格
税込110円(本体価格100円)です。これは通常の楽器メーカー製リコーダー(1,000〜2,000円程度)に比べると桁違いに安い価格です。掃除棒単品と考えても、楽器店で買うと数百円しますから、110円で本体+掃除棒をまるごと買えるのは非常にリーズナブルです。
・品質・音程
100均リコーダーは「おもちゃ」と割り切った方が良いです。音色や音程は精密に調律されておらず、まともに演奏するのは難しいでしょう。実際に100均リコーダーを試した方の報告でも、高音域は多少劣る程度でしたが、低音域になるとチューナーで測っても明らかに音程がズレたとのこと。つまり、指穴の配置や管の設計が正確でなく、音を正しく出す楽器としては不十分なのです。
ただし掃除棒については、100均付属のものでも十分実用に耐えます。プラスチック棒ですので過度な力をかけると折れる可能性はありますが、丁寧に扱えば問題なく使えるでしょう。
・取り扱い店舗
ダイソーの商品ラインナップは店舗の規模や地域によって異なります。文具玩具コーナーが充実している大型店や、新学期前(4月頃)には入荷している可能性が高いです。もしダイソーで見当たらない場合は、セリアやキャンドゥでも類似の商品を扱っています。また、楽器店や通販ではヤマハやアウロス製の掃除棒単品も購入できます。緊急で必要な場合は100均に限らず入手しやすい方法を選ぶと良いでしょう。

リコーダーの掃除棒(クリーニングロッド)とは、リコーダー内部の水分や汚れを拭き取るための細長い棒状の道具です。多くの場合、片方の端に小さな穴が開いており、ここにガーゼや布を通して使用します。
掃除棒に布を巻き付けてリコーダー管内に入れ、内部に残った息の水滴(結露)や唾液由来の汚れを優しく拭き取ることができます。
こうすることで、演奏後のリコーダーを清潔に保ち、カビの発生や嫌な臭いを防ぐ効果があります。
リコーダーは笛の内部に人の息が通る構造上、演奏すると内部に水分が必ず溜まります。一見汚れていないようでも、内部は意外と湿気やホコリが溜まっているものです。
この水滴や湿気を放置すると、雑菌やカビが繁殖しやすくなり、楽器に臭いが付いたり健康上も良くありません。また、水分が管内に残ったままだと音がこもったり、次に演奏する際に「ブー」という音が出る(通称ウォーターロック現象)こともあります。掃除棒で内部を拭き取って乾燥させておくことで、リコーダーを常に良い音で演奏でき、衛生的にも安心なのです。
リコーダーを長く使うためにも掃除棒による手入れは欠かせません。樹脂製リコーダーであれば多少手入れを怠ってもすぐ壊れることはありませんが、それでも内部に汚れが蓄積すると劣化や変色の原因になります。木製リコーダーに至っては、水分放置は厳禁で、ひび割れやカビなど重大なダメージにつながります。「吹いたら拭く」を習慣にすることが、楽器を良好な状態に保つコツです。
以上のように、リコーダー掃除棒はリコーダーのお手入れに必須の道具です。学校で配布されるリコーダーには基本的に付属していますし、市販のリコーダー製品にも掃除棒と専用ガーゼがセットになっているものが多いです。
もし付属の掃除棒を無くしてしまった場合でも、本記事後半で紹介する代用品や入手方法があります。

リコーダーの掃除棒を使った基本的なお手入れ方法を解説します。初めて掃除する方やお子さんと一緒に掃除する保護者の方も、この手順を踏めば安心です。ここでは樹脂製(プラスチック製)リコーダーの掃除方法を扱います。
①掃除棒(クリーニングロッド)
リコーダーに付属のもの、または代用品でもOK(代用品は後述)
②ガーゼや薄手の布
掃除棒に巻いて使います。サイズは30cm×30cm程度の薄い綿布が目安です。市販の「リコーダー専用ガーゼ」があればベストですが、100均の医療用ガーゼや薄手ハンカチで代用可能です。例えば、ダイソーの「用途に合わせてカットできる大判ガーゼ(30cm×100cm 2枚入り)」なら半分に切ればちょうど良いサイズになります。ポイントは薄くて吸水性があり、糸くずが出にくい布を使うことです。
③柔らかい布やクロス
リコーダー外側を拭くための布。眼鏡拭きのような柔らかい布や、使い古しのTシャツ生地などが適しています。
④中性洗剤と容器(必要ならば)
日常の簡易手入れでは不要ですが、週1回程度の徹底掃除で使用します(後述の「徹底洗浄」の項目で説明)。
⑤タオル
洗浄後の拭き取り用。綿タオルを用意しましょう。
まず、リコーダーを分解します。ソプラノリコーダーの場合、通常は頭部管(歌口のある上の部分)と中部管(指穴のある胴体部分)、足部管(一番下の部分)に分かれます。無理に固い場合は無理せず、後の水洗い手順でふやかして外すこともできます。
掃除前に絶対に注意したいのが「歌口のエッジ」に触れないことです。
エッジとは、頭部管の吹き口にある薄い板状の部分で、息が当たって音を作る重要部分です(上記画像の丸印参照)。ここは音を出す命綱となる部分で、エッジを指で押さえたり、掃除棒でゴリゴリしたりすると音が変わってしまうので、掃除の際もエッジ付近は布越しに扱うようにし、直接触れないでください。
また、ジョイント部(管と管の継ぎ目)にはグリス(油)が塗ってある場合があります。掃除の際にベタつくようなら、一旦拭き取っておきましょう。長期間手入れしておらずグリスが固まっている場合は、後述の水洗いで柔らかくしてから拭き取ると良いです。
演奏直後で管内に水滴が多い場合、掃除棒を通す前に水分を飛ばすと効果的です。息を強く吹き込んで内部の水滴を吹き飛ばす方法です。(学校では「水抜き」と教わることもあります)。
このとき、絶対にエッジ部分を手で押さえず、必ず布越しに行ってください。

布を当てずに直接手で押さえて息を吹き込むと、飛沫が飛んで不衛生ですし、指でエッジを傷める恐れもあります。
この工程は必須ではありませんが、特に頭部管内部の水滴が多いときはやっておくと後の掃除が楽になります。
いよいよ掃除棒の出番です!掃除棒にガーゼ(または布)を巻き付けますが、正しい巻き付け方を覚えましょう。
- ガーゼを細長く折る
付属ガーゼの場合、適度な細長い形状になるよう畳んでください。三角形に折ってからクルクル巻く方法もあります。 - ガーゼの一端を掃除棒の穴に通す
掃除棒の先端にある小さな穴に、ガーゼの角を少し通します。ガーゼが厚いと穴に通しづらいですが、無理に詰め込まず、薄く折った角を通すイメージです。 - ガーゼを先端にかぶせ折り返す
ガーゼを穴に通したら、その部分を掃除棒の先端にかぶせるように折り返します。掃除棒の先端を布で包み込む形です。この折り返しによって、掃除棒の先端の硬い部分が布で覆われ、直接管に当たらなくなります。これがとても大事なポイントで、先端がむき出しだとリコーダー内部(特に頭部管の奥やエッジ付近)を傷つける恐れがあるためです。 - ガーゼを巻き付ける
折り返したら、そのまま布の端同士を揃えるように掃除棒にクルクルと巻き付けます。巻く長さは掃除棒の先から5mmほど布越しに余裕を持たせると良いとされています。先端に少し布の厚みを出してクッションにしつつ、棒の長さ方向へ布を巻いていってください。途中でずれないよう、きつめに巻きます。
巻き終わったら、布が外れないよう軽く押さえて保持しましょう。ガーゼが厚すぎる場合は無理に詰め込まず、布を小さく切るなどして調整してください。特にソプラノリコーダーは管が細いので、厚手のハンカチなどだと中で詰まって動かなくなることがあるので注意しましょう。
ガーゼを巻いた掃除棒で、リコーダー管内の水分を拭き取ります。各部位ごとに丁寧に行いましょう。
- 頭部管の内部
頭部管(歌口部分)から掃除棒をゆっくり差し込みます。奥まで突っ込みすぎないように注意してください。特に頭部管の奥にはエッジやブロックがあるため、無理に奥深く突き刺さないことが肝心です。布を巻いた先端が当たったら、その場で軽く回転させるようにして水分を拭き取ります。ゴシゴシと強くこする必要はなく、布に水分を吸わせるイメージです。終わったらゆっくり引き抜きます。 - 中部管(胴部)の内部
中部管の端から掃除棒を通し、管の全長に渡って布が行き渡るように動かします。掃除棒が長い場合は一度で奥まで届きますが、短い場合は両側から差し込んで中央まで拭くと良いでしょう。こちらも軽く回しながら引き抜くことで、内壁全体を拭き取ります。 - 足部管(ある場合)
足部管も同様に内部を拭きます。ソプラノリコーダーでは足部管がないか一体型の場合もあります。
各管それぞれ、数回繰り返して内部が乾燥するまで拭き取りましょう。掃除棒の布がびしょびしょに濡れたら、一度布の乾いた部分に巻き直すか、新しい乾いたガーゼと交換すると良いです。
拭き取りの際、決して乱暴に棒を突っ込んだり押し付けたりしないでください。特に頭部管はデリケートです。優しくシ撫でるくらいの気持ちで十分水分は取れます。
また、頭部管の端(歌口側)に掃除棒を突っ込みすぎると内部の突起に引っかかることがあります。引っかかった場合は無理せず逆側から抜いてください。
丁寧に扱えば、100均付属の掃除棒であっても途中でボキッと折れるようなことはまずありませんが、品質的に強度が低い可能性もあるので力加減には注意しましょう。
内部が拭き終わったら、リコーダーの外側も清潔にします。柔らかい布やクロスで、管体の表面、指穴の周囲、歌口の外側(唇が触れるところ)などを拭きましょう。
特に歌口周辺は口紅や飲み物の汚れが付いていることもありますので、念入りに行いましょう。アルコール除菌シートを使う場合は固く絞ってから表面を優しく拭き、後で乾拭きしてください。(プラスチックにアルコールが長時間残らないように)。
このとき、歌口の内部(ウインドウェイ)には布や綿棒を突っ込まない方が無難です。どうしても水滴が残っている場合は、息を吹き込む方法で飛ばすか、綿棒を使うとしてもそっと水分を吸わせる程度にしましょう。
拭き取りが完了したら、各パーツを陰干しして完全に乾燥させます。水分が少ない場合は拭くだけでOKですが、洗浄した場合や湿気が多い季節は自然乾燥も取り入れましょう。
直射日光や高温はプラスチック変形の原因になるので避け、風通しの良い室内でしばらく乾かします。
リコーダー内部にまだ湿り気が残っている状態でケースに入れて密閉すると、残った水分からカビが生える危険があります。「乾いてから片付ける」を徹底してください。特に夏場や長期休暇中などは、忘れずに乾燥させておきましょう。
乾いたのを確認したら、リコーダーを元通り組み立て、ケースや袋に収納します。ジョイント部にグリスを塗り直す必要がある場合(動きが悪い場合)は、再度薄く塗っておきます。学校配布のリコーダーではジョイントグリスは基本不要ですが、接合が固いときは楽器店で購入できます。
以上が日常的なお手入れの手順です。所要時間は慣れれば数分程度ですので、ぜひ毎回の習慣にしてください。「それでも毎回は大変…」という方もいるかもしれませんが、その場合でも最低週に一度はしっかり掃除することをおすすめします。

日々の掃除棒によるお手入れに加え、週に一度程度はリコーダーを水洗いして徹底的にきれいにしましょう。
特に長期間使ったリコーダーは内部に蓄積した汚れや臭いが取れ、衛生面でも安心です。
プラスチック製リコーダーであれば水洗い可能ですが、木製リコーダーは絶対に水洗いしないでください。
洗面器など容器に水またはぬるま湯(40℃以下)を張り、食器用中性洗剤を少量入れます(1リットルあたり5〜10ml程度が目安)。お湯は熱すぎると楽器が変形する恐れがあるので絶対に避けてください。人肌より少し暖かい程度にします。
分解したリコーダー各部を洗剤入りのぬるま湯に沈め、30〜40分程度放置します。汚れが浮き上がり、殺菌も期待できます。
※頭部管に水が入ると内部のブロック(歌口の木片)が取れるのでは?と心配になるかもしれませんが、学校用の樹脂製リコーダーはブロックも樹脂一体成型なので問題ありません。木製リコーダーの場合は浸け置きNGです。
浸け置き後、容器の中で軽く振るように洗います。スポンジなどでゴシゴシ擦る必要はありません。細かい隙間は綿棒や柔らかいブラシで撫でても良いですが、基本は振り洗いで十分です。歌口から水を通して内側もしっかり洗い流しましょう。
洗剤成分が残らないよう、全パーツを水道水でよくすすぎます。外側に付いた泡も落とします。ジョイント部の古いグリスも、この段階で綺麗に洗い流しましょう。
洗い終わったら、すぐに柔らかいタオルで外側の水気を拭きます。内側も、掃除棒に乾いた布を付けて何度か通し、水気を取ります。特にジョイント部分の穴などに水が残りやすいので注意します。
各部を陰干しし、十分に乾燥させます。室内でOKですが、できれば直射日光の当たらない風通しの良い所に置き、数時間〜半日ほど乾かします。内部に水滴が残らないようにすることが目的です。可能なら、縦置きスタンドに挿すか紐で吊るすなどして、管内に空気が通るようにすると早く乾きます。
水洗い掃除の後は、再度日常のお手入れ手順(ガーゼ拭き取り)を軽く行っておくと完璧です。これでリコーダーは内部までスッキリ清潔になります。「少し皮脂でベタつく?」と感じた場合も、中性洗剤で洗えばすっきりします。
木製リコーダーは上記のような水洗いやアルコール消毒はできません。

「掃除棒を無くしてしまった!」「付属の掃除棒を学校に置き忘れた」など、掃除棒が手元にない場合でも慌てる必要はありません。身近なものでリコーダー掃除棒の代わりになるものはいくつかあります。
- 箸(竹箸・木箸)
家庭にある割り箸や菜箸は長さと細さがちょうど良く、優秀な代用品になります。先端にガーゼや薄布を巻き付けてテープで留め、掃除棒と同じように使用します。このとき布が外れないようにしっかり固定し、テープ部分が露出しないよう布で包んでください。割り箸ならば割って角を削って丸めておくと安心です。菜箸は長いので奥まで届きますが、先端が尖っているものは軽くヤスリがけすると良いでしょう。 - 編み棒(毛糸編み用の棒針)
細くて長い棒針も掃除棒代わりになります。こちらも先端に布を通す穴はないので、布を巻き付けテープ留めで対応しましょう。金属製の場合、先端で傷を付けないよう充分布でカバーします。 - 細長い棒状の掃除グッズ
100均には「すき間掃除用」の棒状クリーナーが売られていますl。例えばエアコンの隙間などを掃除する細長いマイクロファイバー布付き棒(隙間棒)です。これらは最初から先端に布が巻いてあり、形もリコーダー掃除棒に近いため代用可能です。布部分が取り外し式なら清潔なものに交換して使いましょう。布の材質はマイクロファイバーが多く、柔らかく吸水性が高いのでリコーダー内部の水滴拭き取りにも向いています。 - ストロー+ティッシュ
応急処置的な方法ですが、太めのプラスチックストローにティッシュを詰め込んで簡易モップにし、リコーダー内部を拭うという手もあります。ストローの先に布をかぶせて輪ゴムで留めてもOK。ただし強度が低く扱いづらいので、他の方法が無いときの最終手段です。
代用品を使う際の注意点
どの場合でも、先端の硬い部分がむき出しにならないよう必ず布で包むことが重要です。
また、奥まで無理に突っ込みすぎないようにして、リコーダーを傷付けないようにしましょう。代用品は正式な掃除棒に比べて強度や形状が最適でない場合があります。力任せに動かすと折れて中で詰まる危険もゼロではありません。
あくまで「応急用」と割り切り、近いうちに正式な掃除棒(または掃除セット)を入手することをおすすめします。

「毎回掃除するのは正直めんどう…」と思ってしまうかもしれません。しかし、リコーダーの掃除を怠ると様々なトラブルの原因となります。
最大のリスクはこれです。リコーダー内部に唾液由来の水分や汚れが残ったまま放置すると、温度湿度次第でカビが生えて黒ずんだり、嫌な臭いが発生します。特に夏場や長期休みに手入れをサボると、再開時に「中がカビだらけ!」ということも実際にあります。カビ胞子を吸い込むのは健康にも良くないので、衛生面からも掃除は必須です。
内部に汚れや水垢が付着すると、リコーダーの音響特性が変わり、正しい音程が出にくくなることがあります。また、吹き口に唾液が詰まって乾燥すると風の通り道(ウインドウェイ)が狭くなり、音がかすれたり鳴りにくくなります。特に低音域で音がこもる・出ない場合、内部にホコリや繊維クズが溜まっていることもあります。
手入れされていないリコーダーは、ケースの中で不快な臭いを放つようになります。カビ臭や唾液臭が染み付くと取るのが大変です。子どもが嫌がって練習しなくなる原因にもなりかねません。
外側も拭かずにいると、指紋や皮脂でテカテカになったり、汚れが変色したりします。特に白い部分は黄ばみやすいです。美観を保つためにも定期的な清掃が望ましいです。
以上のようなトラブルを防ぐためにも、日頃の掃除習慣が肝心です。もし「最近掃除してなかった…」という場合は、長期休みに洗浄するなどしてリセットしましょう。楽器を清潔に保つことは、良い演奏のための第一歩でもあります。
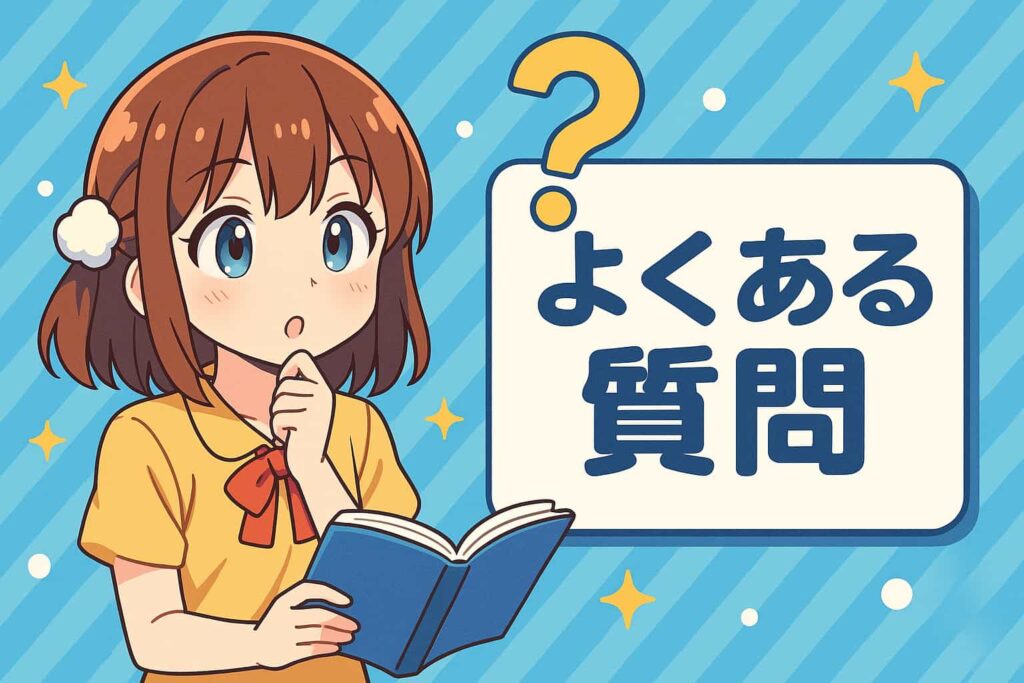
- ダイソーで掃除棒だけ買えませんか?
- 残念ながらダイソーでは掃除棒単品の販売は確認できていません。掃除棒を手に入れるには、ダイソーではリコーダー本体ごと購入する形になります。110円でおもちゃのリコーダー+掃除棒を買って、その掃除棒を使うのが手軽な方法です。どうしても棒だけ欲しい場合は、楽器店や通販で掃除棒単品(例えばゼンオンやアウロスの掃除棒)を購入するか、もしくは本記事で紹介した代用品で代用しましょう。
- リコーダー用のガーゼってどこで買えるの?普通の布じゃダメ?
- リコーダー専用ガーゼは楽器店や文具店で売っていますが、100均の医療用ガーゼで十分代用可能です。実際、教育現場でも「市販のガーゼハンカチを切って使ってください」と案内されることがあります。重要なのは薄手で糸くずが出にくい綿素材であること。端の処理も特に縫う必要はなく、切りっぱなし一重の方がむしろ扱いやすいとされています。ガーゼが手に入らなければ、薄手の木綿手ぬぐいを細長く切ったものなどでもOKです。要は吸水性と柔軟性がポイントです。
- 掃除棒の正しい使い方がいまいち分かりません。子どもにも教えるコツは?
- 掃除棒の使い方は、ぜひお子さんと一緒に実演しながら覚えましょう。手順としては、まず布を掃除棒の穴に通して巻き付ける(先端を布で覆う)、そして優しく中を拭くだけです。難しいテクニックはありませんが、力任せにしないこと、布がずれないようにすることが大事です。もし布巻きがうまくできない場合、市販のリコーダースワブ(紐付きの布を通すだけのクリーニングクロス)を使う手もあります。親子で掃除タイムを楽しみながら、「上手にできたね!」と褒めて習慣化させると良いでしょう。
- プラスチックのリコーダーは本当に水洗いして大丈夫?
- ABS樹脂製のリコーダーなら水洗い可能です。ヤマハ公式のQ&Aでも「水洗いできます」と明言されています。ただし、洗ったあとは必ずガーゼで内部の水分を拭き取り、十分乾燥させることが重要です。また、熱湯は避け、ぬるま湯に留めてください。アルコール消毒も一応できますが、濃度や接触時間によってはプラスチックを傷める可能性があるので、やる場合は柔らかい布に消毒用アルコールを含ませて表面を拭く程度にとどめましょう。
- 掃除をサボってカビ臭くなったリコーダーは復活できますか?
- まずは上記の徹底洗浄を試してください。中性洗剤につけ置きし、しっかりブラッシング&拭き取り→乾燥で、多くの場合臭いは軽減するはずです。それでも臭いが残る場合、重曹水で洗う・アルコールスプレーで殺菌後よく乾燥させる、といった方法もあります。ただしプラスチックを傷めないよう注意が必要です。どうしても取れない酷いカビの場合、買い替えを検討した方が良いケースもあります。臭いが付く前に日頃の掃除を心掛けましょう。
- 学校ではみんな掃除棒使ってないみたいだけど、本当に必要?
- 一昔前に比べ、最近は「演奏後に毎回掃除しましょう」と強制しない先生もいるかもしれません。しかし、上記の通り楽器を清潔に保つメリットは大きいです。子ども達だけでは手入れが行き届かないことも多いので、ご家庭でフォローしてあげると良いでしょう。掃除自体は数分で終わりますし、慣れれば自分でできるようになります。

リコーダーの掃除は、見落とされがちですが楽器を長持ちさせるためにとても重要なお手入れです。
ダイソーでは掃除棒だけの販売は確認できていないものの、掃除棒が付属したリコーダー(玩具)を110円で購入可能です。また、掃除棒が手元にないときは、100均の商品をを活用した代用品でもしっかり掃除することが可能です。
掃除のやり方はとてもシンプルで、慣れてしまえば数分で完了します。演奏後にサッと拭き取るだけで、嫌な臭いやカビを防ぎ、クリアな音を保つことができます。特に子どもが学校で使うリコーダーは、毎日口にするものだからこそ、衛生面にも気を配りたいですね。
ぜひこの記事を参考に、手軽に手に入る100均アイテムや自宅にある道具で、無理なくリコーダーのお手入れ習慣を取り入れてみてください。清潔で気持ちよく演奏できる環境が、楽器との付き合いをもっと楽しくしてくれるはずです。



